

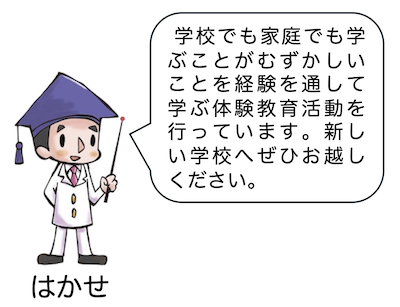
 |
 |
 |
 |
 |
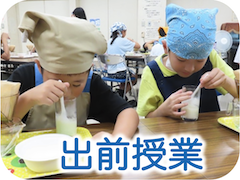 |
 |
 |
 |
 |
 |
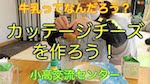 |
 |
2024.05.12
第71回親子農業食育教室「野菜の苗を植えてみよう!」
今回はトマトやナスやピーマンなどの夏野菜の苗を植えるイベントです。講師はJAふくしま未来地域支援課の高田優作先生、インターン生は相馬高校の寺島帆乃香さんです。まず始めに私たちが暮らしている地球の生き物たち(動物、植物、菌)について学び、続いて私たちはそれらを捕まえたり育てたりして、殺して食べてしまっていることを学びました。

次に私たちが食べている野菜や穀物などが植物のどこを食べているのかを理解する「お野菜クイズ」です。植物は一般手的に根・茎・葉・花・果実・種子という器官をもち、私たち人間は植物によってこれらを食べています。これらを1つ1つクイズで出題して答えてもらう、考えてもらうことで野菜が実は植物だといううこと、そして全て子孫を残すために頑張っていることを理解してもらいました。

続いて野菜苗を植えるための畝作りです。めいめい鍬やレーキを持って高田先生に教わったとおり、畝をつくりました。

ここからトマトやナスなどの夏野菜の苗を作った畝に植えていきます。野菜の苗はポットの中で根を張り巡らせていますので、ひっくり返して取り出します。そして畝に穴を掘って、そこに優しく苗を植えました。

続いてさつまいもの苗も植えてもらいました。最後に植えたばかりの苗にジョウロで水をかけてもらいました。

野菜苗の定植の後は屋外調理の時間です。まずは段ボールを細長く切って丸めてかまどに入れる「ダンボールビリビリ」からです。昨年育てたサイエンスラボ米と一昨年仕込んだお味噌を使ったお味噌汁をつくります。子どもたちは薪を効率的に燃やすには並べ方やうちわで空気を送り込むことが有効であることを学びました。

みんなで作ったお昼ご飯をめいめい美味しくいただきました。

最後に(日本語の手話で)科学のポーズで集合写真を撮りました。

2024.04.28
第70回親子農業食育教室「種まきをやってみよう!」
みなさんは最も身近な食べ物の1つであるお米が田んぼで作られていることはご存知ですよね。お米づくりは日本人にとって大変重要なものですので、小学校の5年性で学ぶことになっています。しかし、身近に田んぼがない場合も多いので、土を入れたバケツに稲の苗を植えるところから始まることが多いようです。私たちはお米が稲という植物の種子だということをきちんと理解し、そこから苗を育てて田植えしたものが育つことを体験してもらいたいと思って、毎年お米の種まきからみなさんと一緒にお米づくりを行っています。
今日は第70回の親子農業食育教室「種まきをやってみよう!」です。まず初めに私たち南相馬サイエンスラボが何を目的に活動を行っているかを紹介しました。私たちは「幸せをつくる教育」を活動の指針としています。地球は今から46億年前に誕生したと考えられていて、現在までの長い時間にたくさんの生物が生まれました。生き物は動物、植物、菌の3つに分類され、それぞれが食べたり食べられたり、時には協力し合って暮らしています。

まずは昨年の秋に収穫した稲穂から取り外して保管していた種籾を見てもらいます。いつも食べているお米とは違って殻がついていますよね。この殻を剥いたものが玄米になります。そしてさらにその玄米の周囲の糠(ぬか)と呼ばれるものを削ったものが白米ということになるのです。みなさんには、まずは種籾を1粒ずつ取ってもらって、殻を剥いて玄米にして、それをポリポリ食べてもらいました。美味しいですよね。

次にこの種籾の中から、元気の良い種籾を選び出すことになります。どうやって元気なものを選び出すのでしょうか。それは種籾を水に入れることで選ぶことが出来るのです。みなさんもお米を研いだことがあると思いますが、お米は水に沈むのが当たり前だと思っていませんか?稲穂にはたくさんの種籾がつきますが、実は中身のぎっしり詰まった思い種籾と、あまり中身が詰まっていない軽い種籾があるのです。ここでは種籾の一部を水に入れたビーカーに入れて混ぜてもらいました。そうすることで水に浮かぶ(中身の詰まっていない種籾)と沈む種籾(中身が詰まっている元気な種籾)を分けることが出来るのです。

そうして水に浮かぶ元気のない種籾を捨てると、中身の詰まった元気な種籾だけを選び出すことが出来るのです。実際にはそうして元気な種籾を選び出したら、水が入った大きなバケツの中に沈めて暗くて涼しいところに置いて、毎日水を換える作業を10日ほど行います。そうすると種籾は水を吸って大きく膨らみ、胚芽と呼ばれる部分から白い芽が出てくるのです。
小学校では植物の種から最初に出てくるのは「根っこ」だと習っていると思います。でもそれはアサガオとかヒマワリなどの双葉が出る植物(双子葉植物)の場合なのです。稲はトウモロコシや麦などと同じ単子葉植物ですので、最初に出てくる白い芽は「葉っぱ」なのです。つまりどんな植物でも種から最初に出てくるのは「根っこ」だとは限らないということなのです。
そうしたお勉強が終わったら、次は種まきの作業になります。たくさんの穴が空いたポット苗シートに苗みどりという稲の苗用の培養土を穴の半分くらい入れて、一旦湿らせます。そこに3粒ずつの芽出しをした種籾を蒔いていきます。種籾を蒔き終わったらさらに苗みどりを載せて(覆土)、改めてジョウロで水をかけて作業は完了です。4つのシートに種まきをしたものはサイエンスラボの暖かい場所で苗を育てます。6月初めの田植えに大きく育った苗を田植えしていくことになります。

作業の後はお昼ご飯づくりです。今回は昨年サイエンスラボの田んぼで育てたサイエンスラボ米を炊いたご飯とお味噌汁です。味噌汁には田んぼの周りで採れたツクシなども入っています。味噌は一昨年の冬にみんなで仕込んだ新味噌です。ご飯炊きとお味噌汁づくりは屋外調理(火おこしも)ですので、これを繰り返すと防災スキルが身につくのです。

完成したご飯を食べて今回の「種まきをやってみよう!」は完了です。お疲れ様でした。最後に科学のポーズで集合写真を撮りました。
